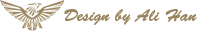ようこそ、秘密異世界相談所へ。(仮)第一章・第一稿
ようこそ、秘密異世界相談所へ(仮)。
第一章
体育なんて、するもんじゃない。
疲れるし、汗かくし。
けれども、学校のカリキュラムでそう決まっているのだから、仕方がない。
人は、大きな力の前では無力なのだ。
それでも、人は生きてゆかなきゃならない。
この、現実の中で。
伊波礼司《いなみ・れいじ》はそんなことを思いながら、私立秋津洲《あきつしま》学園高等部の、赤紫色のブレザーに着替え終え、自分のクラスである2-Bに戻ってきた。
教室の一番窓側、後ろから二番目の、自分の席の前にたどり着く。
そして大きくため息を一つつき、席についた。
同年代からすれば大人びて見え、大人になったら童顔に見える、いわゆる年齢不詳な顔の礼司は、無表情な顔で周囲を見渡した。
体育の授業後の、休み時間。
教室は、クラスメイト達の話す声で満ちていた。
礼司は彼らの声をBGMにしながら、教室の大きな窓から見える、静かな青空と、それに色とりどりの屋根の二階建て住宅に、ところどころマンションやビルが生えている、平和な秋津洲市の街並みをぼんやりと眺めていた。
その時だった。
彼の前の席に、金髪碧眼で気品高い顔立ちの、いわゆる美少女と呼ぶにふさわしい美貌の──日本人は西洋人を見ると、誰もを美人と錯覚しがちなのだけれども──留学生、アルティナ=トルニアが、彼と同じように、疲れた表情で帰ってきた。
帰ってくるなり、勢いよく、しかし綺麗に椅子に座り、ゆっくりと机に体を落とす。
彼女の、頭の後方左右で二房に分けた長い金髪が、太陽を受けてキラキラ輝く黄金色の湖面のように、ぱっと輝いて広がる。
礼司にはその様子が、白鳥が湖で翼を休める様子に、似ているようにも思えた。
それから彼女は、だるさを目一杯含んだ小声で、こうつぶやいた。
「ふぅ……。疲れてマナが足りませんの……。あとで『ひいそ』で補充しましょうか……」
と。
礼司はそのつぶやきに、
(また、か。また『ひいそ』か。こいつはいつも、こういうことをつぶやく……)
顔をしかめ、彼女の背中に広がる、金髪の大海から目をそらす。
それは、彼女と同じクラスになってから始まったことだった。
*
彼女の奇妙なつぶやきが始まったのは、約一ヶ月前。
高校二年生になり、すぐのこと。
それは、傾いた赤い日の光が、教室に暖かく差し込む、放課後のことだった。
一日のすべての授業を終え、礼司は教科書などを鞄にしまっていた。
そこにある友人が、声をかけてきた。
「おーい、礼司ー。遊びに行かないかー?」
「ああ、ちょっと待ってくれ。すぐ行く」
そんな他愛もないやり取りをしながら、カバンに色々なものをしまいこんでいた所だった。
その時だった。彼の机の前に動きがあったのは。
そこは留学してきたばかりの留学生、アルティナ=トルニアの席だった。
背高で、長い金髪を二房に分けた、赤紫色のブレザーを着た青い目の、どこかしら気品さを感じさせる美少女の彼女。
そこにちょっと背が低い、黒髪でショートヘアーの、赤い縁のメガネをかけた、落ち着いた風貌の少女がやってきた。
そこまではいい。よくあることだと礼司は思う。
ふたりとも留学生だし、連れ立ってどこかへ行くというのはあるだろうし。
それは理解できたけれども。
奇妙だったのは、二人が交わした会話の内容だった。
それは……。
「ねえ、セイレン。今日『ひいそ』へ行きますか?」
「ひ……、アルティナさんが言うなら行きますけどね。
最近はもめごとが多いのであまり行きたくないのですが。何が楽しいんでしょうね?」
そのアルティナはいったん窓の方を見る。
そして、おもちゃを欲しがる子どものような声でつぶやいた。
「……もし、あの方を誘えたのなら、『ひいそ』がもっと楽しくなるのにね……。
さ、行きましょうか」
「ええ、アルティナさん」
そう言いながらアルティナは席を立ち、セイレンと呼ばれた留学生とともに、教室を後にしていった。
その会話を無言で聞いていた彼だったが、彼女らが去った後、内心で絶叫した。
(『ひそく』……? なんなんだ。今の会話。この二人……厨二病か?
……。
ああ、あいつらに呼ばれてたっけ。行かなきゃ……)
そう思い直し、荷物を全部カバンに入れて、礼司は椅子から立ち上がった。
(それにしても……懐かしいな)
と礼司は窓の向こうに映る、遠くの景色を眺めた。
いつもと変わらない、秋津州市の平和な光景だった。
そして、自分の机から離れ、教室を出ながら、思う。
自分にも、ああいうことを思う頃があった。
マンガや文庫を読んで、そういうことを妄想する時期があった。
しかしそれもあの時、すべてを失った後で、そんなことを思うのはやめた。
自分は現実を知ったからだ。
自分は、大きな力の前では無力であると。
あの頃信じていた異世界も、魔法も、奇跡も、異能も、超科学も、何も実在しない。
VRMMORPGで、敵を次々と切り倒し、俺TUEEEEEができる世界もない。
物質をすべてエネルギー転換する魔法で、何もかも吹き飛ばせる事ができる世界もない。
遠い宇宙で光の剣を振りかざして、暗黒の騎士と戦う世界もない。
右手で異能をかき消せることができる世界もない。
ここに今いる世界。自分の世界。
それがすべてであり、真実で、現実だ。
だが、あの時見た「あれ」は現実だった。真実だった。
現実だから、皆、失われたのだ。
彼は傲慢と思えるほど、そう信じていた。
いや、信じさせられていた。思い知らされていた。
けれども。
彼女の言葉を聴いていると、やはり懐かしさと興味が湧き上がる。
彼女たちが話している事について聞いてみたい、と思うこともある。
けれども、その事について聞いてしまえば負けだ、という思いが礼司のどこかにあった。
だから、彼女に訊けなかった。訊こうとしなかった。
なぜなら、礼司には自分の悩みがあったからだ。
訊けば、自分の悩み。
そして、自分の望みを話すことになるのでは、と恐れていたからだ。
礼司の悩み。それは。
自分のクラスについての馴染めなさについてだった。
いじめられたりとか、仲間はずれにされたりとか、そういうわけではなかった。
むしろクラスの皆との仲は良かった。
が、どことなく、学校に、クラスに居づらいとは思っていた。
自分と皆とは違う、と感じていた。
その理由は自分でもわかっていた。
家族がいないこと、だった。
自分には父方と母方、両方の祖父母や叔父叔母などが健在で、かれらが礼司の生活費や学費などを出してくれていたから、生活には困っていなかった。
それでも、家に帰ると誰もいない、というのは寂しく、かなしいものだった。
家に帰った後の、流れてくる空気はひんやり冷たく。
電気器具の動作する音がわずかに届いてくるだけ、というのは、彼にとって辛いものだった。
しかし、それを学校の他の誰にも言えずにいた。
言えば皆を辛くすると知っていた。
だから、心は辛くても、明るくふるまっていた。そういうふりをしていた。
生きていよう。
生き続けていれば、きっと、あいつは見つかる。
そして、復讐してやる。
礼司は、そう望んでいたから。
それが、礼司の望みだった。
一つかわいた息を吐く。
自分とアルティナの席を、ちらりと見た後で、礼司は教室を出た。
*
……そうこうしているうちに、一ヶ月が流れていった。
彼女、そしてその友達との厨二病話は、断続的に聞こえていた。
異世界。
術法と彼女らが呼んでいる魔法。
魔法使い。
宇宙人。
超能力者。
異能使い。
モンスター。
怪人。
そして、『ひいそ』という謎のキーワード。
教室で自分と彼女(と友だち)が一緒にいるときに、わざとらしくそんなわけのわからないことばかりを話すものだから、
(自分にわざと聴かせるんじゃないのか、これは)
礼司は、机に突っ伏したり勉強したりしながら盗み聞きしては、そう疑ったりする。
彼女のそんな厨二病な残念な点を除けば、金髪碧眼で端正な美少女だった。
背が高くて胸は大きいし、性格も明るくて皆に気づかいができて人気者だし、いい物件なんじゃないかな、と礼司は思っていたりしていた。
そこに、今のアルティナの独り言。
(またか。『ひいそ』)
彼女の言葉に、思わず耳をそば立ててしまう。
気がつけば、彼女の一挙一動が気になってしまい、自分がかつて、そんな人間だったことをつい思い出してしまう。
(いけないいけない。俺はあの世界から離れたんだ。現実はここにある世界だけ。
異世界なんてありはしないんだ)
そうかぶりをふるも、どこか懐かしさをつい感じてしまうのであった。
懐かしさ。
そう思うと、礼司はふと、自分のスポーツバッグをまさぐっていた。
そして、ある一冊の文庫をそっと取り出だした。
じっと、礼司はそのちょっとだけしなびれた文庫本を見つめる。
夜の森のイラストを表紙にしたその文庫は、携帯や財布などとともに、『あの日』礼司が持っていたものだった。
とある王国と、そこにある暗い夜の森で繰り広げられる、魔物の王と少女の幻想的な恋物語。
礼司は今は読むことはなかったが、表紙を見るだけで、風に揺れる夜の森の光景が思い浮かぶ。
その文庫には、家族と過ごした思い出が詰まっていた。
あの時彼を守り、今の彼を守ってくれているお守りだった。
礼司は優しく、緑の森に立つ、白い少女を見つめていた。
その時、チャイムが鳴った。
そしてチャイムと同時に、次の授業の担任が入ってきた。
(授業か)
礼司は慌てて文庫を机の中にしまい、カバンから教科書やノートを取り出し、授業に集中することにした。
文庫のことなんて、頭の中からすっかり抜け落ちていた。
*
その日の授業が全て終わり、日が傾き、校舎を赤く照らしている放課後のことだった。
校舎の玄関口を出ようとした礼司は、ふと、あることを思い出した。
忘れ物を、だ。
(いかん、大事な本を机の中にしまったままか)
それに気がついた礼司は、慌てて下駄箱に戻り、靴を履き替えると、ダッシュで教室へ向かった。
(多分盗られてるとかそういうことはないだろうけど、あれは大事なものだ。
持ってないと)
急ぎ足で教室へ向かう。
走ってはいけない廊下をダッシュで駆け抜け、角を猛スピードで曲がる。
普段なら一段ずつ登る階段を、二段飛ばしで登る。
走っているのに、教室へ向かういつもの道が、やけに長く、遠く思えた。
「はぁ……、はぁ……」
ようやくのことで、たどり着いた。
教室の扉の上に付けられた「2-B」の札。
息を切らしながらそれを確認すると、後ろの扉を勢い良く横に引く。
そして、彼は目を疑った。
そこは教室のはずだった。
机と椅子が行儀よく並べられ、タイルが敷き詰められ、天井には蛍光灯が取り付けてある、いつもの教室。
その教室が、深く暗い、夜の森になっていた。
天井は暗い夜の空となり、空には満月が輝いていた。
机と椅子は硬く太い木々になり、床には草が生え、風が優しく吹いていた。
どこからか動物や虫の鳴き声が聞こえ、メロディーを奏でていた。
あの本の世界、夜の森が、そこに、あった。
そして一つだけ、木々の間に置かれていた、机と椅子──そこは礼司の机と椅子だった──の上に。
あの留学生、アルティナ=トルニアが座って、礼司の本を読んでいた。
彼女のそのたたずまいは、まるで『夜の森の真昼姫』のようであった。
(あれは……。まさか)
礼司はその瞬間、言葉にならず、持っていたカバンとスポーツバッグを取り落とす。
ただただ、その光景を見つめていた。
が、アルティナの手にあるものを見つけ、我に返った。
そして大きな声で叫び、教室へと足を踏み入れる。
「トルニアさん。これはどういうことだ。なぜその本を持っている?」
本を読んでいたアルティナは、彼の強い水鉄砲のような声に撃たれ、
「い、伊波さんっ!? ななななんで!?」
慌てた顔で、同じくらい大きな声で撃ち返した。
その瞬間、夜の森はかき消え、いつもの何もない教室に戻っていた。
そして、座っていた机から降り、文庫本を机の上に置くと、
「……みましたわねー?」
美少女的な表情から、目と口の端を吊り上げ、妖しい美女の表情へと変わったかと思うと、その青い目が金色に光った。
……アルティナは何かを仕掛けてきた!
その目を見た途端、礼司は何かを言おうとして、何も言えなくなった。
どこに隠れていたのかわからない、彼女の美しさ、いや妖しさが体全体から漂ってくる。
(なんでだろう……)
今なら彼女の言うことなら、なんでも聞いてしまいそうな気がする。
そう予想したとおりに、彼女はこう命令してきた。
はちみつの川のような甘い声で。
「ねえ……、伊波くん……。これからわたくしの言うことを──」
その時だった。
鼻がむずむずしたのか、アルティナは言葉の途中で、くしゅん、と一つくしゃみをしてしまった。
その瞬間。
ドンッ! と言う大きな音がして、彼女の周りから爆風が、津波のように飛んだ。
その爆風に飲み込まれ、幾つもの机と椅子が宙に飛ぶ!
爆風と椅子と机の波は、あっという間に礼司の方向へと広がって行く。
そして……。
ドッシャン! ガラガラガラアアン!!
という、幾つもの木と鉄パイプと床のタイルが叩き合う音が、何度も巻き起こった。
しばらくして、音がやむ。
爆発の時、顔を腕で覆っていたアルティナが、腕を外して目を開けると。
礼司のいた、教室後方の扉のあたりには、机と椅子がうず高く積み上がっていた。
「い、伊波くんっ!?」
*
アルティナのくしゃみにより(?)、飛び散らかった机や椅子などが、礼司がいたあたりに埋もれ、小さな山を作った。
埃が火山の噴火のように巻き上がり、そして静かに舞い落ちる。
それをしばらく呆然と見ていたアルティナだった。
が、礼司が埋もれたのではないか、と我に返ると、
「い、伊波くんっ!?」
一つ叫ぶと、慌てて小山のもとに駆け寄った。
そして大きな声で呼びかける。
「伊波くんっ!? 伊波くんっ!? 大丈夫ですの!? 大丈夫ですの!?」
机と椅子の山の中からは、まったく返事がない。
静寂を保ったままだ。
「……伊波くん!?」
彼女は叫びながら、自分に近い机や椅子を持ち上げ、近くに放り投げるように置く。
その作業を何度も繰り返しながら、
「なんでこんな時に失敗しちゃうの!? わたくしのバカッ! バカッ! バカーっ!!
……うっ、エグエグ」
彼女は泣きじゃくっていた。
しかし、礼司の姿はまだ見えない。
彼女が机を掘り出しながら、さらに、
「伊波くんっ!?」
と呼びかけた時だった。
「トルニアさん……。うるさいぞ。周りに聞こえる」
という声が全く別の方向から聞こえてきた。
アルティナがべそをかきながら、そちらの方へ顔を向ける。
いつの間にか、礼司は教室の前方の扉に立っていた。
そして、ちょっと頭の横を手のひらで抑えながら、こんなことを言う。
「なぜ泣きながら俺を呼んでいる?」
「え……?」
一体、どういうことなのか。
混乱したアルティナの頭では、理解できない様子だった。
「どっ、どっどうして巻き込まれなかったの? もしかしてあなたも術法使いなの!?」
アルティナは驚きながら、礼司のもとに駆け寄る。
そしていきなり飛びつくように、抱きついた。
彼女の重みが、彼の体にのしかかり、礼司の体が後ろに傾く。
「ん!?」
礼司は傾きを抑えて踏ん張る。
アルティナの驚きと喜びが入り混じった顔を見ながら、彼はへ? という困惑とも呆然とも取れる顔を見せていた。
どうやらいきなり抱きつかれたり、術法使いと呼ばれたりして、困惑しているらしい。
その困惑した顔のまま、礼司は当たり前、というような声色で、
「どうしてかだと? 机や椅子が飛んできたから、教室の出口から逃げたのだが?」
そう説明した。
どうやら、机が飛んでくるのを見て出口から飛び出し、難を逃れたらしい。
最初はその言葉に、え、という顔をアルティナは見せていた。
が。それが理解できたのか、突然、顔を朝焼けの海のように真っ赤にすると、
「ひどいっ! ひどいでございますのっ!」
泣きだしながらアルティナは、礼司の頭をぽかぽかと叩いた。
礼司はなぜ自分が叩かれるのかわからないまま、
「頭を本気でぶつな!」
と抗議した。
その言葉に、アルティナははっとして手を止めると、さらに顔の朝焼けが真っ赤になり、
「ごっ、ごめんなさい!?」
慌てて礼司から離れ、少し距離をおいた。
それから、さっと顔を伏せてしまう。
礼司も、はあっ、と言う顔で顔を伏せてしまう。
そのまま二人は黙り込んでしまった。
外のグラウンドでのスポーツ部員の声や、吹奏楽部の演奏の音などが、二人の耳に聞こえていた。
しかし、聞きたいことがある様子で、礼司はゆっくりと顔を上げる。
そして、アルティナに声をかけた。
「しかし、トルニアさん。あれはどういうわけだ」
礼司の問いのあと、沈黙が二人の間を流れていく。
だが、何かを決意したのか、アルティナは伏せていた顔を上げる。
その何かを決意した表情に、何を話すんだろうか、と礼司は興味を引かれた。
彼女は一つうなずくと、すたすたと歩き、自分の席へ向かうと、椅子に座った。
礼司もそれに誘われて、自分の席に座る。
それを確認すると、アルティナはある話をし始めた。
とても重要な話を。
「んーとね、これから言うことは、地球人の皆には、秘密にして欲しいんですけれども。
わたくしは、実はアークシャードという世界にある、ザウエニア皇国という国の人間です。
あなた達から見るとわたくしは異世界人、なんです」
「……アークシャード? ザウエニア? 異世界人?」
「ええ、そういう世界と国があるのです」
彼女は一つうなずいた。
そして、小川のようによどみなく流れる言葉で、話を続ける。
彼女の話は、礼司にとって信じがたい話だった。
が、彼女の口調は、真剣そのものだった。
それに、彼女のしゃべり方は、同じ年とは思えないほどとても落ち着いている。
年上や、高貴な身分の人間と話しているような空気が、流れていた。
「貴方達の世界の時間で、一年前の夏休みのこと。
ザウエニアで神々が、幾人かの地球人を召喚したの。世界間の戦いに備えるために。
そして彼らは、世界を股にかける長い戦いの後、地球に帰ってきたの。
でも地球の時間では、その間数日しか流れていなかったの」
「……」
「戦いが終わり、神々の助けで地球に帰ろうとしたその時、ある事件が起きて、異世界と地球の間に恒久的な門《ゲート》がつながってしまったの。
それを利用して、様々な異世界人が地球にやってきて、この国の政府と密約を結んで、普通の地球人には秘密で暮らし始めたの。地球のことを知るために。
わたくしも、その一人というわけなの。
それがわたくしたちがこの学校にいて、魔法を使える理由。そういうわけなんです」
彼女の話はそれで終わった。
しばらく、二人の間に再び沈黙が流れた。
その沈黙の堤防を破るように、礼司は驚きと疑いが入り混じった顔で、芝居がかったような声で返す。
「そんな世界が、いくつもあるのか」
「伊波くん、まだ信じてないのー?」
「そんなことない。信じている。ただ幻覚みたいなものを見てしまったが」
「ほら信じていませんし! あれは本物です! 術法です! 魔法です!」
「君が俺に何かしようととしてくしゃみして勝手にキレて、机と椅子を蹴飛ばしたのだろう。
あれに巻き込まるところだった」
「ああっ、記憶がなんか混濁しているっ? 魅了の術法が失敗したから、記憶がおかしな方向に書き換わっているのかしら!? ここは記憶を全部消した方がいいかも!?」
「何を変なことを言っているんだ? やっぱりお前は厨二病か?」
「わたくしは厨二病なんかじゃありません! ……って」
アルティナの返しは少し感情的なものであったが、それでも丁寧さや気品の良さ、また育ちの良さが感じられる口調だった。
顔を近づけあいながら、言い合っていたその最中。
アルティナは何かを思い出した様子で、突然自分の体を引き、落ち着いた顔を整える。
礼司はそれに面食らう。
「なんだ?」
「……そういえば、何故伊波くんは、教室に戻ってきたの?」
「ああ。……忘れ物を取りに来た」
そう弁解しながら、礼司は机の上にあった文庫本を、宝石を持つように大事に手にする。
アルティナも、緑の背表紙の本を宝石のように見つめる。
「この本を取りに来たの……」
「どうしてこの本を読んでいた」
「わたくしもちょっと忘れ物がありまして、教室に戻って来ましたら、あなたの机の中に本があるのが見えまして、つい……」
「勝手に人の本を読むな」
「その点に関しては本当に申し訳ありませんでした……。
でも、なぜその本をそのように大事になさっているのでしょうか……?」
アルティナの問いに、礼司は顔を伏せ、黙ってしまった。
彼女は、その様子に、触れてはならない何かに触れたと確信した。
申し訳ない、と言う顔で、礼司の顔をのぞき込む。
気がついたか気づかずか、礼司はやがて、顔を上げた。
遠い海を見るような目で、話し始める。
教室に入る光の加減により、礼司の顔は半分影ががっていた。
アルティナにとって、それはまるで、彼が半分闇の世界にいるように見えた。
「……実は俺、家族をみんな亡くしている。警察は交通事故と言っているが」
「交通事故、ですか?」
「そうだ」
礼司は文庫から彼女に視線を移すと、昔話を続ける。
彼にとって、思い出したくない昔話を。
礼司は一度、目を閉じる。
あの時の光景が、脳裏によみがえる。
その光景を思い出しながら、ゆっくりと礼司は話し続ける。
「……一年前のことだ。
俺は中学校を卒業して、旅行に出かけた。
親父とお袋と、妹の美也子とで、車に載って。
この本とかも一緒に持って、出かけた。
そして車に載って皆と話していた、その時だ。
目の前で、何かが光った。
それから突然、大きな衝撃が襲ってきて、目の前が暗くなった。
何かがバキボキと潰される音と、親父達の悲鳴。
それが聞こえた後、俺は意識を失っていた。
気がついたら、病院のベッドで、色々なチューブに繋がれて寝かされていた。
そばで爺さんや婆さんたちが、心配そうに見つめてた。
父さんたちは? と聞くと、悲しそうに首を横に振って、
皆死んだ。大型トラックにぶつかって、
と告げられた。
生き残ったのは、俺だけだ。
葬式にも出られなかった。
誰もいない家に帰って、仏壇前に置かれた三つの骨壷を見た時に。
皆、死んだのだと。
そう思って、泣こうとしたけど、泣けなかった。
ただ、これが現実なんだ、ということだけは、身にしみて分かった。
そして、それからずっと自分の家で一人、暮らしてた。
そういうわけなんだ」
「そうだったの……」
礼司は首を縦に振った。
それから、大きくため息を付いて、首を数回横に振る。
アルティナは、彼のすぐ近くに座っていた。
なのに、とてもとても、彼が遠くにいるような気がした。
「だが」
「だけど?」
「あれは事故じゃない。何者かが皆を殺したんだ」
「殺した……」
アルティナは礼司の過激な言葉に息を呑んだ。
そして、彼の次の言葉を待つ様子を見せる。
「俺は見た。どこからか放たれた白い光のようなものが、トラックの前を通り過ぎるのを。
その光をトラックが避けたおかげで、俺達の車にぶつかったんだ。
その光を放ったものが、皆を殺した」
「……」
「けれど、俺が車の外に放り出された後、体が冷えていくのを感じながら、もうだめだと思っていた時だった。
誰かがやってきて、何かをつぶやくのが闇の奥底で聞こえた。
不思議な言葉で、体が暖かくなるのを感じて、俺はそのまま気を失った。
その誰かの不思議な言葉がなければ、俺は死んでいたかもしれない。
そいつには、とても感謝している」
自身と確信に満ちた礼司の声に押されたのか、アルティナはただ黙って聴くのみだ。
礼司は言葉を続ける。
手にした文庫の方に、目を移しながら。
「俺も昔は本を読んだりアニメを見たりして、空想の世界を考えたりしていた。
異世界も、魔法も、超能力も、宇宙人も、異能もどこかにあると信じてた。
そんなものは、想像の世界だけだと思っていた。
でもあの事故で、俺は思い知らされた。
そういう世界は、必ず何処かにある。
あの光は、この世界のものじゃない。その世界の何者かが、皆を殺したんだ、と。
俺はあの日から、そのかたきを探し続けている」
「……」
「この文庫は妹も読んでいた、大事な思い出だ。
でも、これを読むと、昔のことを思い出してしまって辛くなるから、読んではいない。
お守りとして、持っている。あの時の自分を守ってくれたお守りとして」
「だからこうまで大事に……」
話を聞いて、アルティナは同情する目を見せた。
だがその目の奥深くには、なにか別のものが見え隠れしているようにも見えた。
「俺はそいつを見つけ出し、復讐する。
そいつを見つけたら、殺すかもしれない。たとえ他の皆が止めても。力がかなわなくても。
絶対に見つけ出し、親と美也子のかたきを取る」
「……」
彼女はしばらくなにかを考えていた様子だった。
が、やがて礼司の目をしっかり見つめ、こう告げる。
「伊波くん。あなたが探しているものは、すぐ近くににいるかもしれません。
たとえば、この世界の隣に」
「この世界の、隣に……?」
「ええ」
アルティナは力強くうなずいた。
礼司はしばらく黙っていたが、しばらくすると、突然、さっきのような冗談だろ、という風な表情になる。
「……そんな世界が、本当にあるのか」
「あるですの!」
「そんなもんあったら世界のバランスが色々と変わっている。侵略とかされているだろう?」
「今までゲートがなかったから他の世界は知らなかっただけなの!
神々も秘密になされておられてましたし!」
「どうして秘密にしていたんだ」
「知ると他の世界にも知られるからですし!」
「それは、全部お前の妄想か? そういう厨二病ごっこを皆としているだけかもしれない」
「術法を見たじゃないですか! わたくしが創りだした、夜の森を!」
「あれは俺の見た幻じゃないのか」
「本物の術法です! 魔法です! 幻術です!」
「ならなぜそんなことしていた」
「本の表紙と文章の描写が良かったので、再現してみようかと、つい……」
「本当か……? それに、他に証拠はあるのか?」
詰め寄る礼司に、アルティナは感情を込めながらも、品の良い口調で返していく。
それでも疑う様子の礼司に、アルティナはうーんと海よりも深く考える様子で目を閉じた。
色々と証拠はありますけどねえ……。
というような素振りでちらっ、ちらっと、アルティナは礼司を見た。
しばらくして、うん! と一つ大きく頷く。
そして、アルティナは、満月のような満面の笑みで、礼司にこう告げた。
「そうです! あなたがわたくしたちのクラブに入ればいいのです!
世界の秘密を共有するクラブに!
わたくしたちのクラブに入って、新しい世界に行きましょう!
そうすればあなたもきっと信じるはずです!」
彼女の輝きは、まさに夜よりも明るかった。
そして、笑顔を保ちながら、
「ねえ、あなたは……。犯人を見つけたくない?」
そう問いかける笑顔が、どことなく妖しく、美しく、ぱあっと広がる。
アルティナの笑顔に、礼司は不思議な魅惑を感じた。
彼女のペースに飲まれてしまってもいいのか。
彼女を信じてもいいのか。
けれども。
彼女の言うとおり、そのクラブに行けば、犯人が見つかるのではないか。
家族のかたきが、自分の復讐が、果たせるのではないか。
礼司の中では、そういう様々な気持ちが、ないまぜになっていた。
入り混じった気持ちのまま、礼司は疑問を返す。
「異世界人とやらが集まるクラブが、どうしてこの学校にあるんだ?」
「学校は学び舎であり、様々な人々が集まりやすい場所ですし。
警察などの権力の力が及びにくいところですので。
それに、ザウエニアに召喚された人達が通っているのがこの学校ですし。
さらに言うと、ゲートがある場所がここに近い。
以上が、この学校にクラブがあるという理由なのですよ」
「なるほど、理屈はあっているな」
「じゃ、ちょっとついてきてくださいな。クラブの場所に案内いたします」
「そこに行けば、新しい世界に出会えるのか。本当に?」
「ええ、必ずです!」
そう言って、アルティナは自信たっぷりの笑顔を見せた。
アルティナの笑顔に、礼司は信じていいのかもな、と感じた。
そう思う間もなく、
「ほら、行きましょう! 伊波くん!」
「待て。カバンとかが」
礼司の声に構わず、アルティナは立ち上がる。
それから片手で自分のカバンなどを手にし、片方の手で礼司の手を取る。
そして、引っ張って立ち上がらせる。
妹や母親以外の女子の手に触れ、礼司はそのぬくもりに心臓が、一つ高鳴った。
(あまりにも無防備じゃないか?)
という思いと、
(……これが女の子のぬくもりというものか!)
という思い。
二つの思いがまぜこぜになりながら、礼司は引っ張られていく。
気を取られすぎて、床に何が転がっているか、失念していた。
倒れていた椅子か机の脚に、彼の足がごつん、とつまずいた。
礼司は大きくバランスを崩し、転がった!
彼の体が、柔道の投げ技のように、アルティナの体を巻き込む!
二人はもつれるようにして、机と椅子の間の床に倒れていく!
ドッシャンガラリーンという、轟音とともに衝撃!
礼司の頭と体に、ずきん、と痛みが走る!
「グワーッ!」
そして……。
彼は痛みにしばらく意識がぼんやりしていた。
が、頭を振って、そのぼんやりを吹き飛ばす。
背中に、硬い床の感触。
そして体の下腹部に柔らかい重みが。
「う、うん……」
と気がつくと。
自分の体の上に、アルティナが乗っかっていた。
赤紫色のブレザーが形作るラインが、大きな二つの胸を強調する。
その下乳、そしてアルティナの頬を赤く染めた顔を見て、礼司も頬が赤く染まる。
鼓動の波が早く、狭く押し寄せるのを感じている。
(こいつ、こんなに肉感があるのか)
そう礼司が内心で感じた時、
「ごっ、ごめんなさい! だっ、大丈夫ですか!? 怪我などありませんですか!?」
アルティナが、朝焼けの空のように、頬を真っ赤に染めながら謝ってきた。
そして、不意に黙ってしまった。
彼女も、鼓動の波が次々と押し寄せている様子だった。
礼司もどうすればいいのかわからず、黙りこんで、動こうとしなかった。
このまま時が止まってしまえたら。
そんな礼司の柄にもないフレーズが、頭の片隅でよぎった。
しばらく無言だったアルティナだったが、ややあって、恥ずかしそうに声を上げた。
「い、いまおどきいたします……」
言いながらアルティナが、体を動かそうとしたその時。
教室の扉近くで足音がした。
二人が起き上がりながらそちらの方を見ると、人影が一つ。
その影は……。
アルティナとよく一緒にいる女子だった。
留学生の、メガネショートヘアで無表情の彼女だ。
たしか、セイレンとか言ったと、礼司は記憶していた。
彼女の姿を見ると、礼司の鼓動の波が、更に速く押し寄せる。
まさに津波のようだ。
彼は何か言おうかと、口を開こうとした。
が、それよりも早く、その留学生の女子が口を開く。
「なにをしているのですか姫様。教室でいたそうなど、なんて度胸がよろしいのやら。
そのままことに及べばよかったですのに。
……話は全て聞いておりました。その男、伊波礼司を入部させようというのですね。
私の一存では何も出来ませんが、個人的にはよろしいと思います」
「せ、セイレン、あんた相変わらずね……。あ、ありがとう……。
伊波くん。わたくしが部長とかに掛けあってみる。多分入部できると思うわ」
(このセイレンとやらは、アルティナの味方か。いつもいたしな)
と礼司はホッとした表情を見せた。
アルティナも、ホッとした表情で立ち上がる。
そして慌ててブレザーを整える。
体が軽くなったのを感じながら、礼司も立ち上がる。
それから、彼女らの言葉に目を丸くした。
「姫様……?」
「あ、言い忘れておりました」
そう言いながらアルティナは左手で制服のスカートをつまみ、膝を曲げた。
物語のお姫様がそうするように。
そして、頭をたれながら、こう挨拶する。
「わたくし、アルティナ=フィメル=レティス=トルニア。
ザウエニア皇国の一国、トルニア王国の第二王女でございます。
以後お見知りおきをよろしくお願いいたします」
「……」
「こちらはセイレン。
セイレン・フィメル・イクストラ・メイガス。わたくしのおつきの侍女なの。
ちょっと無口で毒舌だけど、優しいから安心してね」
その言葉に、セイレンは黙って体を折る。
二人の佇まいは、王女とおつきの者との、それだったけれども。
礼司には、それでもまだ、少し信じがたいところもあったけれども。
それよりも、彼女と、その彼女の話に惹かれていった。
異世界は、あるんじゃないか。
そして、自分の復讐が果たせるのではないかと。
「さっ、行きましょ。今日の部活動はもう始まっているはずですし」
そうアルティナに促され、礼司はカバンと、忘れ物の大事な文庫本を手にする。
それから、彼女らとともに教室を後にしようとしたが、
「……散らかした机と椅子、そのままにしておいていいのか」
疑問が頭に浮かび、そう問いかける。
するとセイレンが平然とした顔で応える。
「下々の者に掃除させておきますので、大丈夫です。さあ、参りましょう」
「それならいいが、本当か」
「ご心配なさらずに。さあ」
と急かすので、礼司は後ろ髪ひかれつつ、教室を後にした。
*
「どこへ行く?」
秋津州学園の西日さす廊下を抜け、玄関に出て、靴を履き替えて外に出る。
礼司は先を行くアルティナたちの背中に、問いを投げかける。
当然といえば当然すぎる問いである。
アルティナは問いを背中で受け止めると、歩きながら少しだけ振り返る。
「文系部室棟よ」
振り返った時に揺れた金髪が、陽の光を浴び、海面のようにきらめいた。
礼司はそのさまに、きれいだな、という印象を心に刻み込んだ。
そんな礼司をよそに、アルティナは言葉を続ける。
「学園には、異世界に関連したクラブが、幾つもあるのよ。
大きいのはそれこそ何百人もいるけど……」
「何百人、か」
「大学や学校に通ってない方も所属していますからね。でもわたくしたちのクラブは違うの。
部員がわたくしとセイレン含めて五名しかいないの」
「それは同好会というが」
「そうともいうわね」
アルティナのあっさり認める具合に、礼司はずっこける!
それから態勢を取り戻し、続けて問いかける。
「その同好会で、何をやっている?」
「えーっと……」
「主に他の異世界人の悩み事の受付と、その解決でございます」
アルティナへの質問に、セイレンが見事な割り込み発言だ!
「他の秘密異世界クラブや、外の世界でのトラブルを、親切丁寧に解決する秘密クラブ。
それが私ども、『ひいくお悩み解決相談所』でございます」
「コマーシャル的だな」
「で、わたくしたちのクラブはそういうことをしているの。表向きの活動目的もね」
「ああ。うちの学校って、いろいろ奇妙な部活があるな。散歩部、とか」
「……ああ、あの部活ですか」
その何かの意味をふくんだアルティナの発言に、礼司はまさか、と身構える!
「あれねー。ザウエニアとかの冒険者が始めた部活なのよねー。
色々なところをほっつき歩いているみたいだけど、何やってんだか……。
最近ではダイス振って出た目の乗り物や行き先に行くとかしているみたいだけど。
……莫っ迦じゃないの?」
「水曜どうでしょう、か」
「なにそれ?」
「そういうテレビ番組がある」
「テレビ、ですか……。あー、一日中つまらない芸を垂れ流している魔法の鏡ねー。
あれ見てると眠くなるから、寝るのにはちょうどいいわよねー」
「ディスり芸か」
「なんですの? 『でぃすりげい』って?」
「世の中には知らなくてもいい言葉がある」
二人が見事な会話のラリー芸をしている間にも、彼らは文系部活棟に到着した。
文系部活棟に入ると、どことなく空気と雰囲気が変わった。
中高大と、三つの学校が併設されている秋津洲学園では、文系クラブ棟も理系クラブ棟も、そして体育会系棟も、それぞれ中高大の部活がひとまとめにされて建設されている。
文系クラブ棟の陣容は、例えるならクリスタルの塔だ。
そこでは日々健全なものから妖しげなものまで、様々なクラブが活動している。
そのクリスタルの塔の、中層階に礼司たちはいた。
片方は白い壁とズラッと並んだドア。
もう片方は廊下を挟み、青いガラスが廊下の向こう側まで続いている。
その白い廊下を、アルティナと礼司、そしてセイレンが歩いていた。
礼司は歩きながら、なにか匂いをかぐようにあたりを見渡す。
そして、
「アルティナ」
「なんでございますの? 礼司さん?」
「あたりの雰囲気が、外と違う」
礼司はそうつぶやくように疑問を投げた。
実際、礼司はある奇妙な匂いを感じていた。
そして、違う世界が見えていた。
それは、花や草木などにも、食べ物の匂いにも、香水にも似た、それでいて、そのどれでもない匂い。
眼の前に広がるのは、赤青黄紫、その他の光の粒が入り混じった、色とりどりの光の波。
「この匂い、この景色は……」
「あら、伊波くんにも見えるの? 『マナ』が」
「マナ?」
首をひねる礼司。
アルティナはそっと手を上げ、目の前で流れるマナの流れをすくった。
光の波が、乱れ、つぶとなって、手のひらにすくい上げられる。
「わたくし達の世界や、その他の魔法世界で、魔法を使うときに消費される物質。それがマナ。
世界によってその形や色などは異なりますけど。
ここでは、様々な世界のマナを混ぜて粒状にして流しているのですよ」
「とすると……」
「そう、この階と近くの階は、異世界関係のクラブが多く入っているのです」
言うと同時に、彼女の足が止まる。
礼司も足を止める。
三人の目の前には。
何の変哲もない部室の白いドアが、ある。
そしてそばにあった名札には。
「相談部」
という文字が書かれてあった。
その名札を見ては、礼司が声を上げる。
「相談部?」
「そう。それがワタクシ達の部活です。
……じゃ、部長に話してくるから、ちょっと待ってて」
そう言って彼女は片開きドアを開き、部室の中へと消えていった。
閉じられるドア。礼司はセイレンと二人ぼっちになる。
礼司は壁に体を預け、わずかに下を向く。
しばしの、無言。
マナの河が、ただ静かに空中を流れる。
礼司はその流れを見ながら、ぽつん、とつぶやく。
「なあ。セイレンさん」
「なんでしょうか?」
「魔法は、あるんだな」
「ええ」
「その魔法を俺も、使えるのか?」
「わかりません。ただ、才能が有るのなら、使えるでしょう」
「そうか……」
そう噛み締めるようにつぶやいた礼司に、セイレンが無表情をわずかに変え、不思議そうな顔を見せる。
「なぜ、そのようなことを訊くのです?」
「なぜって……」
その、なぜ、という問いが、分からない顔を礼司は見せる。
答えはわかっているだろう、というように。
「決まっている。俺は皆を殺したかたきを、取りたいからだ」
「……」
その答えに、セイレンはまた無表情に戻る。
静寂も、戻る。
だが、その静寂は、長く続かなかった。
部室のドアが、勢いよく開かれたのだ。
笑顔のアルティアの顔が、ひょい、とそこからのぞく。
「おまたせしました! どうぞ! 伊波くん!」
アルティアの言葉に、ふっ、と顔を上げ、礼司は体を壁から離した。
そして一度うなずく。
ああ。と。
そしてドアから、部室の中へと入っていった。
玄関から中へと、一歩踏み出した途端。
「……ジ。……イジ」
ささやく声が、一つ聞こえた。
彼はその声を聞いて、顔をしかめる。
なんだこの声は。
だが、それはすぐ近くにいる誰かの声ではなく、もっと遠くから聞こえてくる『誰か』の声に思えた。
空耳か。
礼司はそう一人で合点すると、アルティアの後に続く。
部室の入り口は左に給湯器や冷蔵庫など、右に扉だ。
おそらく、トイレだろう。
そして奥へと入ると。
そこは長方形の二〇畳ほどはあろうかという部屋だ。
真ん中には学校などでよく見かける折りたたみ式の机が二つ横に並べられ、その周りを金属とゴム製の折りたたみ式の椅子が取り囲んでいる。
壁際には長机と、いくつかの細々とした道具や紙など。
壁には学園でよく見かけるお知らせなどのポスターが貼ってある。
その向こう側は白いパーティションがある。
おそらく、倉庫代わりとしているのだろうと、礼司は思った。
パーティションと机の間の椅子。
いわゆる誕生日席に、赤紫を基調とした秋津州学園高等部のブレザーを着た男子が、その部屋の主としての威厳を見せるように座っている。
彼の両脇には、同じく秋津州学園高等部のブレザーを着た女子がひとりずつ立っていた。
彼女らの顔は、日本人のそれではなく、アルティナや、セイレンのそれと同じく、異国人のものであった。
だが、背丈はアルティナと比べると、さほど高くない。
そして男に視線を戻すと。
顔は今時の若者相応という顔であったが、体つきは違った。
制服のラインからのぞく、首が太い。腕が太い。体つきが大きく硬い。
彼の体はどこかで鍛えたようでもあり、機械的でもあるラインであった。
その顔。その人を、礼司は知っている。
秋津州学園高等部副生徒会長、天宮猛士だ。
なぜ、あなたがここに。
礼司がそう問いを投げかける前に。
猛士は立ち上がり、その体つきに似合わぬひょうひょうとした笑顔を礼司に向け、こう呼びかけた。
「伊波礼司くん。ようこそ、『秘密異世界相談所』へ」
と。
本作品の無断転載などを禁止します。
あいざわゆう。
2月 24, 2013 日曜日 at 11:30 am