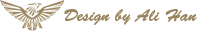新作削り。
剣の姫巫女≪メイデン≫と大命者≪ヘスター≫(仮)
あいざわゆう
第一章:
その「啓示」は、突然ネットを渡ってきた。
何事も無く日常をぼんやりと過ごしていた僕に、目覚めてくれというように。
それはそう、週の真ん中の水曜日のことだった。
僕、克哉・石塚・マルカーンが、一面茜色に染まる空の下、学校の帰り、スクールバスから降りた時だ。
秋津洲市と呼ばれるこの街の、ターミナル駅の前に降り立ち、何かネットでも見ようかな、と思い立った時だった。
メガネ型透過ディスプレイの片隅に、ツイッターのダイレクトメッセージを示すアイコンが点滅したのだ。
ん、なんだろう。こんな時にダイレクトメッセージなんて。
そのメッセージアイコンを、脳波で押した。
DMの名前と彼女を示すアイコンと共に、表示されたのは……。
「あたし、アタシアタシ」
「……ってピカティじゃないか……?」
一気に目が覚めた。
そのメッセージを見た途端、可愛くて心のある声が心のなかで聞こえてきた。
挨拶に、こんな三〇年前ぐらいのネタを使うなんて……!
その場にずっこけながら、僕はすかさず、脳波入力でツッコミのダイレクトメッセージを投げた。
ちなみに彼女とは、ザウエニアの一地方の、アラビア文字に似ているような文字でやりとりしている。
「で、なんでございましょうか。ピカトリクス・フィメル・アミール・イスマイル・フィルーン王女。突然DMなんて投げられて? そちら≪ザウエニア≫はいかがでしょうか?」
姿勢を元に戻しながら、脳波操作で文字を入力する。
さて、ちょっと一休みできる場所を探すか。
その時だった。
「どったの?」
不思議そうな少女の声が、そばから呼びかける。
僕の地球での幼なじみ、山吹芽衣子だ。
一緒にスクールバスから降りてきた彼女の問いに、俺は言葉を濁して返す。
「ん、ああ。ちょっとツイッター」
長い黒髪を後ろで一つにまとめて、波のようにゆらゆらと揺れる髪型。
個人的には、まあ美少女なんじゃないかと思える利発的で可愛い顔つき。
中肉中背の体を赤紫のワンピースの制服を着込んだ芽衣子。
彼女も、メガネ型ディスプレイをかけている。
すぐさま、ピカティからメッセージが返ってきた。
「あたしピカティ、今この街におりますの。助けて、ください」
「はい?」
僕は思わず声を上げた。
ピカティは向こうの世界<ザウエニア>のイズマイル王国という国のお姫様で、絶賛お姫様ライフ中だ。
ザウエニアとは、異世界との接触の時に最初に地球に接触した、魔法がある世界でありながら、地球をはるかに超えた科学技術なども持ち合わせた異世界だ。
僕の父親、ルシャーム・メル・アミール・ハティム・マルカーンの故郷≪ふるさと≫でもある。
正確に言うと、世界名は<アークシャード≪天空のかけら≫>と言う。
ザウエニアとは、アークシャードにある、北アメリカ大陸に似た大陸のことを指したり、そこにある神々と皇王、その下にいる国王などが治める、幾つもの国が集まって構成されている皇国を指すこともある。
そんな異世界アークシャードに住んでいるはずのピカティが、どうしてこの地球に、この秋津洲に、いるんだ?
それに……。『助けて、ください』って……。
僕は急いで電話機能を開き、ピカティの個人電話番号にかける。
素早くリストを選択。名前を押す。国際電話番号を使わずにだ。
電話は、すぐに繋がった。世界間通信でよくある長めのタイムラグはない。
ということは、この地球にいるのか?
携帯の念話スイッチを入れる。
今の時代のスマホは、精神波を読み取り、言葉を念じるだけでそれを音声に変換し、相手に送ることができるのだ。
これで芽衣子に内容を聞かれることなく、話ができる。
「もしもし、ピカトリクス王女様?」
「はいー」
聞き慣れた、優しく甘くて気品ある声が日本語で返ってきた。たしかに姫様だ。
術法やボイスチェンジャーで声を変えているのでなければ、だが。
それはともかく、聞きたいことを聞いてみる。
「なあ、今本当に秋津洲におられるのですか?」
「はい。いますの」
「おられますか」
「いますの」
それはそれとして、王女様、転送門≪ポータル≫でこっちにやってきたのか……。
久しぶりだなあ。
それはともかく、聞きたいことはまだある。
むしろそっちがメインだ。
「……どうしてこっちに来られたのですか?」
僕がそう言った瞬間、電話はぷつっと、切れた。
「もしもし? もーしもーし?」
だが、耳元から聞こえるのは、プーップーッという電子音のみ。
ふぅっ。……しょうがない。こっちから出向くか。
僕は神殿街へと足を向けた。
幾つものJR線や私鉄、それに新交通システムなどが乗り入れる秋津洲駅は、いつも人でごった返している。
いつもの光景。いつもの場所。
それがなんだか、くっきりと輪郭を持って見える。
神殿街は、駅からやや離れたところに入り口がある。
新交通の駅が神殿街の近くにあるけど、そう大した距離ではないし、歩いていこう。
「克哉、どったの?」
山吹芽衣子が、不思議そうな顔のまま、僕の後を追う。
同じクラスの芽衣子は、僕がこっちに戻ってきてからの幼なじみだ。
おせっかい焼きなやつだが……。
あ? 彼女じゃないからな?
言っとくけどただの幼なじみだからな? うん。
それはともかくとして。
僕はそんな世話やきで、可愛い彼女に言う。
「んー、ちょっと神殿街。知り合いが来てるらしい」
話は間違ってはいないな、うん。
「ふーん。知り合いねえ……」
背中からそんな疑問の声が飛んでくる。
ま、こいつはいつもそんなんだが。僕は良く女子と絡むせいだろうな。疑われるのもしょうがないか。
内心頭をかきながら、神殿街の方を視る。
今僕達がいるのは、秋津洲駅前だ。
今は古い、建設当時は未来的なデザインの駅ビルやデパート、都市ビルが並び立つこの街は、異世界人たちが数多く居住する国際都市になっている。
地球人から見れば見慣れない建物や、見たことのない文字のアドホログラム≪看板≫などがここからでも見える。
バスターミナルに面した通りでは、ここかしこで異界の鮮やかな民族衣装の人間や、見た目が人間とはまるっきり違う二足歩行型生物や、意識を持って歩く人間型ロボットなどの異世界人、そして日本人や外国人といった地球人たちが行き交っている。
一般の日本人からしてみれば、そこは日本ではない、いや、地球ですらないどこかにいるようにも錯覚する、エキゾチックで魅惑的な場所だ。
そんな人々の間をすり抜けながら、僕はザウエニア人街に向かう。
芽衣子も横についてくる。
……相変わらず目を細めて疑わしい目つきをしているけど。
早くピカティの待つ、ザウエニア人神殿街のファスラム教神殿≪モスク≫へと行こうか。
と、その時、突然、ディスプレイに着信のアイコンが忙しく光った。
相手は……、もちろんわかってる。王女様だ。
僕は脳波コントロールで電話機能を立ち上げる。
「もしもし?」
すると、先ほどと同じ、抑揚のないきれいな声が聞こえてきた。
「あたしピカティ。今パブコにおりますの。……ちょっと、急ぎます」
「だからなんでメリーさんなんですか!?」
それはともかく、パブコというのは、ザウエニア人街の近くにある大型デパートのことだ。
ちょっとずつは近づいてきているらしい。
……王女様、楽しんでいらっしゃいますね?
「ちょっと待っててください。すぐ参りますので」
僕がそう言うと、電話はすぐに切れた。
……姫様、お聞きになられてるのかなー?
僕はパブコへと足どりも軽く向けようとした。
と、そう言えば。
王女様、向こうで神殿で姫巫女≪メイデン≫の修行をしてて、この間、全修行を終えたとおっしゃっていたっけ。
彼女からはこの間、そちらのアーマギアのご修行はいかがですか? なんて尋ねられたけど。
……ん?
音だ。
「何か」が空を飛び、空気を震わせて切り裂く音。
間違いない。あれは……。
僕が空を見上げると同時に、つられて、芽衣子も空を見上げる。
ビルとビルの間の空を、機械の箒に乗った魔法使いや、空飛ぶ車などが行き交っていた。
その更に上を、人型の機械が四体、轟音を立てて駆け抜けていく。
人型の機体は、二メートルから三メートルぐらいの大きさで、近未来的で鋭角的な、戦車とも、航空機とも、はたまた甲冑的とも取れるデザインをしている。
「アーマギアだ」
「そだね」
僕らは二人して当たり前のように頷き、アーマギアたちを見送った。
アーマギア。それは「パワードスーツ」のザウエニアでの呼び方だ。
パワードスーツとは説明不要かもしれないけど、動力アシストのついた装甲服、と思って貰えればいいと思う。
異世界と接触する直前のアメリカ合衆国で、このパワードスーツが実用寸前だった。
だけど、ザウエニアやその他の世界が実用化し、実戦投入したパワードスーツやアーマギアは、その性能を凌駕していた。
アーマギアは地面を歩き、重量物を背負って戦う、ただの装甲歩兵ではなかった。
歩兵のサイズで戦艦以上の火力と防御力を有し、それらが戦闘機以上の速度と機動力で陸海空、そして宇宙を駆け巡るアーマギアに、地球各国の軍部は恐怖した。
第一次地球大戦終結後、アーマギアの技術は地球へと流出し、一般にも広く使われるようになった。今ではアーマギアを使ったスポーツも数多く存在し、クラブチームなどがその覇を競っているのだ。
だからアーマギア使いやそれを扱う職業とかは、地球人の若者には憧れの的になっているんだけど。
……。
あーあ。
「あーあ、それにしてもアーマギア科なんて選ぶんじゃなかったよ」
自然にため息が漏れる。
その溜息に応じて、横から声が飛ぶ。
「あんたが選んだんでしょ。納得しなさいよ」
……芽衣子の突っ込みは本当に容赦ないよなあ。
「アーマギア科」とは学校で呼ばれている通称で、正式には「機動甲冑科」と言う。
ちなみに、僕が通う私立秋津洲学園には、様々な世界から来た異世界人たちのために、様々な学科がある。
アーマギア科はそんな中でも最も華やかな学科の一つで、僕はそんな学科で悪戦苦闘しているのだ。
「だって、アーマギア競技とかで使うほとんどの術法が使えないんだぜ、僕は……。
あーあ。なんで選んじゃったんだろう。アーマギア科なんて。
でも、アーマギア製作者≪マイスター≫という道があったから、よかったけどね……」
僕が苦笑すると、
「まっ、あんたがなんでアーマギア科を志望したか、あたしには丸々お見通しですけどね。
……この嘘つき! ナマケモノ!」
そうなじって芽衣子は僕の片足を強く踏む。
いてて! 思わず僕は飛び上がる。
そんな僕を見て、芽衣子がニンマリと笑った時だった。
「克哉、芽衣子とアツアツだな!」
「ヒューヒューっ!」
後方から飛んできた野次に、僕らは同時に振り向く。
場所は駅前の広場、線路沿いの通りで、地下通路へと続く階段を覆うクリスタルドームの前、地球人や異世界人が忙しく行き交う、夕暮れの時間だった。
そこに、ホームルームのクラスメイトである、黒田彗星≪くろだ・こめっと≫たちがそこにいた。
彼らも秋津洲学園から直帰らしく、僕達が載ったスクールバスのすぐあとに出たスクールバスに乗って秋津洲駅までやってきたようだった。
……彗星≪こいつ≫の佇まいも、周りの光景に押されて、どこか窮屈に見えるなあ。
「アツアツなんかじゃねえ!」
僕はふてくされ顔で返す。
「アーマギア科なんかより、ビジネス系を選んだほうが良かったのに。世の中カネだぜ、金」
クラスメイトの悪友たちの中心にいた彗星は、笑って言った。
「聞いていたのかよ……。盗み聞きは泥棒の始まりだぞ」
「そんなことわざ、聞いたことがないぞ」
「今作った。ま、嘘つき、を盗み聞きに変えただけだけど」
僕はさらにうそぶいた。
彗星は、ビジネス科を学んでいる。将来は起業して、大儲けしたいんだそうだ。
……そういえば彗星、貧乏な家なんだよな。
私立の秋津洲学園にも、奨学金で入って、学校帰りにはバイトしているらしいし。
「ビジネスを勉強して起業しても、金持ちになれると保証されるわけでもないけどなあ」
続けざまに僕は言う。
アツアツ、なんて冷やかされたお返しだ。
それに……。
「それに、どこかの起業家が本に書いたことよりも、近くの自営業のおっさんおばさんとかの話を聞いたほうがいいと思う。地に足をつけたほうがいいよ。失敗して無一文になったらどうするんだ?」
今の言葉は偽ざる僕の思いだった。
だが、僕の言葉に、彗星はまゆをわずかにしかめた。
駅の通路に、冷たい糸をまとわせた風が吹き抜ける。
「克哉。お前はその名前に違わず古臭いよなあ。やっぱりシバレスの血が混じっているからか?」
彗星の言葉に、今度は僕がむっとする番だった。
こいつ……。
「俺は『何者か』になりたい。名前の有る、力のある何者かに。
そのために俺はビジネス科へ通っているんだ」
「……」
「『何者か』であること自体、『何者でもない』者よりもずっと幸せなんだぜ? ……わかってるか? シバレスであるお前は、それを自覚してるのかよ!」
怒気を込めながら、彗星は僕のブレザーの袖を強くつかむ。
「おい! 黒田!」
「よせよ!」
周りの友人達が慌てて割って止める。
……それは、そうだ。そうだけど……。
首もとをきつく締められながら、僕は振り絞るように応える。
「……僕だって、まだ、何もないんだよ……!」
言いながら、思わず僕は腕を薙いだ瞬間。
彗星は荒天の強風に吹かれた木の葉のように軽々と飛んでいって、コンクリートの地面に見えない手でたたきつけられる。
あ……! しまった……!
周りの通行人たちが、大きな衝撃音で一斉にこちらを向く。
「うがあっ!」
「彗星≪コメット≫、大丈夫か!? ……ごめん」
謝罪しながら、倒れた彗星のもとに駆け寄る。
シバレスとしての力が強すぎて、軽く振り払ったつもりが、吹き飛ばしてしまったのだ。
やっちゃった……。
重たい後悔の念が頭を駆け巡りながら、僕は彼を優しく抱き起こす。
が、彗星≪コメット≫は忌々しい顔で、
「それを『持っている』って言うんだよ……!」
と言って僕の手を振り払い、自分で起き上がり、クラスメイトの元へと小走りに向かう。
彼の足元の影が、黒く長く伸びていた。魔界の生き物のように。
僕はその影を直視できなかった。
そんなわけない。
「そんなわけないよ。こんな力を持っていたって……。いいことは、ないんだ」
僕は暗く俯きながら、その場を離れた。
そんな僕を、芽衣子が慌てて追う。
「おい、どこへ行くんだよ!」
クラスメイトの一人の声が、背中から投げかけられる。
僕はその声に振り向かない。
……振り向くもんか。
「……ちょっと知り合いを迎えに、神殿街まで……」
その言葉に嘘はない。ないし。
「そうか……。じゃあな」
「じゃあなー」
友人が声をかける。
彗星の挨拶は、なかった。
*
「ねえ、そんなにむくれてないでよお」
背中から山吹芽衣子の声が追いかけてくる。
僕と芽衣子は彗星≪コメット≫たちと別れてから、ピカトリクスがいるというバブコへと向かっていた。
大型家電量販店が入居している、商業ビルディングなどの間を通る通りを通りぬけ、大通りの横断歩道で信号が青になるのを待っていた。
だけど、僕の気持ちは収まらない。
さっきのあいつの言葉に。自分の行動に、立場に、思いに。イラつく。
その気持ちを抑えるように、僕は応える。
「むくれてなんかないよ」
「ううん、むくれてる。あんた、怒ってる」
つられたように芽衣子の声も怒っている。
「……」
彼女の怒りには無言で通し、青になった信号を確認して横断歩道を渡る。
細めの通りを入ったところにあるアミューズメントセンター「ラッシー」の前に来た時だった。
その時、メガネ型ディスプレイにまた着信のアイコンが輝いた。着信アイコンにスイッチ。
「もしもし?」
その問いに帰ってきた返事が聞こえたその瞬間、気分も、世界も、一八〇度変わった。
「あたしピカティ。今ラッシーの中におりますの。はやく、きて」
「ラッシー!?」
俺は思わず、ホログラムの飛行機が屋上に乗っかって輝いている、赤い建物を横目で見ながらすっとんきょうな「声」を上げる。
「い、今参ります」
そう言うとまた不意に電話は切れた。
なんてこった……。姫様がこんなに早くこっちに近づいてきているなんて……。
何故か、背筋に冷たいものが走る。
けど、さっきの彗星≪コメット≫に感じた冷たく暗いものとは、大違いだ。
「どったの?」
芽衣子が顔を傾けて聞いてきた。
「あ、ラッシーに入ろう。ご来賓がここにいるみたいなんで」
言いながら俺はラッシーのガラス張りの自動ドアの前へと進む。
「ご来賓……?」
芽衣子の不審そうな顔を視界の隅に捉えながら、僕はラッシーへと足を踏み入れた。
入るとすぐそこにはゲーセンらしく、薄暗い空間の中に、いくつものゲーム機があった。
入った瞬間に、電子音と人工音声が両耳を覆い尽くす。
目の前には、白いドームがいくつも並んでいる。
少し遠くには、そのドームに大きさなどは似ているが、形やデザインの違う筐体がそれぞれまとまって置かれている。
それらはすべて「マジカルリアリティゲーム」の筐体だ。
マジカルリアリティゲームは異世界からもたらされた技術によって、実現したゲームだ。
<アークシャード>などからもたらされた、世界を創造する「魔法」によって作られた人工空間に、プレイヤーが入り、様々なルールのもとでプレイする、バーチャルリアリティゲームがさらに進化したゲームの事だ。
でも、どちらかというとマジカルリアリティゲームよりも、昔のゲームのほうが好きかなあ、僕は。そっちのほうが面白いし。
シバレスだからという理由で、絡まれるということもないし。
様々な形や色のドーム群の間をすり抜け、ピカティの姿を探す。
しかし、それらしい姿は視えない。
どうしたんだろう……、姫様。また移動しちゃったのかな……。
そう訝しんだ時、ディスプレイの隅に、着信アイコンが光った。急いで電話に出る。
「もしもし?」
しばらくの無言。
……ま、間違い電話かな?
「あたしピカティ」
先程から聞き慣れた声。
楽しいけど、もう飽きたよ、この芸……。
と思った時。
彼女が、今までとは違ったおどろおどろしい声で、続けた。
「……今、アナタたちの後ろにおりますの!」
「え……?」
え……!? ま、まさか……!?
僕が恐る恐る振り向くと。
そこには真っ白な一枚布に包まれたような人影が、佇んでいた。
まるで都市伝説の少女、メリーさんのように!
「いたあああああああ!!」
次の瞬間、僕は思わず絶叫してしまった。
そばにいた芽衣子も、振り返ったらしく、同じような表情で、
「なあにいいいいいい!?」
と釣られて絶叫した。
怖えええ!? 怖えええよなにこれ!?
目の前の白い布に覆われていた幽霊のような人影はしばらく佇んでいたが、腕らしき場所を動かすと、頭の部分に手をかける。
……一体何が出てくるんだ!?
ゴーストか!? ファントムか!? それともヴァンパイアだったりする!? ねえ!?
人影は頭のフードを取る。その間の黒い影から現れたのは……。
「もう、何を驚かれているんですか、カツヤさまっ?」
長い黒髪を後頭部でまとめた、可愛らしい美少女の顔だった。
彼女のその目はくりっとしていて、紫がかった黒。
目のバランスは全体からしてみると大きいが、とても可愛げがあって美しい。
肌の色は雪色で、頬の雪原に赤い花畑が咲いていた。
一対の目の間にそびえる鼻は、低くもなければ高くもなく、綺麗に尖っている。
そして小さく可愛げの有る口。
それらのパーツが、両耳にたれた黒髪の間の小さな顔の中に、最も調和している位置に置かれていた。
彼女はどことなく、庭に咲いた一つの小さな桜の木のようにも思えた。
ほっ……。間違いない。
「あ、ああ……。おひさしぶりです。ピカトリクス王女様……」
目の前にたたずむ幽霊の正体は、見間違わなかった。
ザウエニアにあるイスマイル王国の美姫。ピカトリクス・フィメル・アミール・イスマイル・フィルーン王女だった。
彼女が脱いだフードの間から、体に焚き染めた香の芳しい香りが届いてくる。
ああ……。この気持ちいい匂い。間違いない。ピカティの体の香りだ。
胸に手を当てて一礼した僕を前に、王女は、あ、うん。この場ではね……。というような表情をしてから、深々とおじぎを返す。
「お久しぶりでございます、カツヤ様。あら、このお方は……?」
隣でびっくりしたまま硬直している芽衣子を、ちょっと理解できない、という目で見る。
「なんでそんなにびっくりなされているのですか……?」
「そりゃそうだわっ!! 突然後ろに幽霊みたいのがいたらだれでも驚くわっ!?」
硬直から解けた芽衣子が、両手両足を下手くそなダンスのようにバタバタさせながら、目の前にいるアラブ風民族衣装の少女に、全力で抗議する。
そ、そりゃ、そうだよな。僕だって、驚いたし……。
そんな彼女に王女はすました顔で、
「あら、幽霊≪アンデッド≫なんて、ザウエニアにはいくらでもいますし、そんなに驚かなくても……」
「……これだから魔法の実在するファンタジー世界はっ!!」
「ファンタジー……? わたくし達にとってザウエニアは幻想物語≪ファンタジー≫ではなく、現実≪リアル≫ですし……」
「くっ……」
言いながら二人は、喧嘩をしている犬のように睨み合う。
しかし、敵意を露わにしているのは芽衣子の方で、ピカティはどこ吹く風、余裕の表情だ。
芽衣子……。出会った時から勝負あった感じで、どうするんだ。
その時、何かに気がついた様子で、突然芽衣子は僕の方を向き、質問してきた。
「そういえばこの娘、一体何者なのよ……?」
「ああ。そういえば、まだ紹介していなかったっけ。
このお方は、ザウエニアにあるイスマイル王国の王女、ピカトリクス・フィメル・アミール・イスマイル・フィルーン王女だよ。芽衣子」
「あ、うん」
そう言われて、芽衣子は姿勢を正す。
「これは失礼しました。ピカトリクス王女様。私、克哉・ズルカルナイン・メル・アミール・ハティム・石塚・マルカーンの友人である、山吹芽衣子と申します。以後お見知り置きを」
そう挨拶して、芽衣子は胸に片手を当てておじぎをする。
「こちらこそよろしくお願い致します。メイコさん」
ピカティも胸に片手を当てて挨拶する。
秋津洲学園では様々な世界の王族・貴族などの、上流階級の子息などが留学していることも多いので、こうした礼儀作法は小等部の頃から習わされている。
ま、芽衣子が空気を読める子でよかった。
その顔に浮かび上がる敵意は相変わらずだけど。頭を抱えたいよ。
……ん? 僕ら、いや、ピカティに注がれている熱い視線がある……?
アーマギア科の実戦授業の時のように、素早く周りを見回す。
すると、周りのゲームの順番待ちやプレイを見学していた男達の目が、ピカティの美貌に注がれていた。
彼らの顔は、一様に下衆だ。
……お前ら、姫様をジロジロと見るなよ! こんなところから、すぐに出なきゃ!
次の瞬間、僕はピカティの白くて細い手を取り、引っ張る。
「ピカティ王女様。ここじゃ人の目もありますし、別の場所へ参りましょう」
「え……!? は、はい……!」
と、二人で出口の方へと向かおうとした瞬間だった。
世界が、揺れた。
細かい揺れが何度か連続し、ゲーセン内で悲鳴がいくつも上がる。
「じ、地震!?」
「いや違う!」
慌てる芽衣子を制しながら、僕は王女様の手を放した。
そのまま、ラッシーの出口へと向かうけど、二つの足音がついてくる。
「カツヤ様!? どこへ!?」
「ちょ、チョット待ってよ!? どこへ行くのよ!?」
虚を突かれた様子の芽衣子が、慌てて後を追いかけてくる。
「ちょっと待ってろ! 外を確かめてくる!」
二人にはそう告げるが、僕の命令を無視して二人はついてくる。
ピカティが「助けて」と言ったのが本当のことだとすれば……!
僕がラッシーから一歩踏み出した、その時だった。
ん……!? 殺気!?
すかさず、僕は大声で叫んだ。
「伏せて!」
「なっ、なに!?」
芽衣子が叫んだ次の瞬間、爆発音と衝撃が、殴りかかってきた。
とっさに右腕を目の前に突き出す。
と同時に、集中する。
急な知恵熱のように、頭が熱くなる。
つきだした手のひらの前に白い光が集まり、輝く。
その途端、襲いかかってきた爆発の衝撃と熱と破片が、目の前で止まり、光の中へとかき消える。
「……!」
姫様がその様子に、声を上げた様子だった。
姫様は僕の力を知っているのか? いや、それよりも、こいつらが何者か、確かめないと。
爆発が収まりかける前に、僕はぐるりとあたりを見た。
ラッシーの前の道に。空に。
十体程度の一様に不気味な黒いアーマギアが、槍や銃などの武器を構え、僕らをカメラで見つめていた。
そのカメラが、一斉に赤く妖しく輝く。
こいつらは学校の授業でよく見たことがある。
「無人アーマギア、<スケアクロウ>か」
「ザウエニアでよく使われている歩兵型無人アーマギアね……」
芽衣子の震える声に、僕はただ一度頷く。
姫様が、「たすけて」と言ったのは。
こいつらに追われてたせいか! 何とかしないと!
僕は後ろをちらりと見た。
左手をつないだピカティが、不安そうな目で僕と、目の前の光景を見つめている。
僕はその表情を落ち着かせるように、精一杯の勇気を持って告げた。
「王女様。僕が何とかいたします。……あれらを止めればいいのでしょう?」
そして手を放し、一歩踏み出す。
怖いけど。怖いけれども、今彼女をお守りできるのは、この僕しかいないんだ!
僕の能力≪ちから≫さえあれば、奴らを止められる! やるしかないんだ!
自然と拳に込めるが強まった。
やるぞ、と自分を奮い立たせ、<スケアクロウ>たちをにらみつけた時だった。
僕の脳内に、神々しく、力強い声が響き渡ったのは。
<待つのだ! 我が息子らよ!>
この声は……!
次の瞬間、さっきの光よりさらに白い光が視界を遮る。
「!」
「何よこれ!?」
二人の叫びとともに、僕らは白光に包まれた。
そして、前も後ろも右も左も上も下も、全てが白という世界に、僕らはいた。
「ここは?」
と芽衣子が言おうとした時だった。
<マルカーンの息子ズルカンナインよ、フィルーンの娘ピカトリクスよ。
我はここに存在せり……>
このお声は!
その、世界をも割る、遠いようで近い轟音に、僕とピカティはその場に伏せる。
そしてほぼ同時に、声を合わせおののいた。
「アル=アーン様……!」
アル=アーン様。
それは、僕やピカティが信仰するザウエニアの宗教の一つ、ファスラム教の唯一神様だ。
異世界であるザウエニアにも、当然のことながら宗教は数多く存在する。
例えば、
2月 5, 2014 水曜日 at 1:30 pm