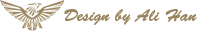削ってみてさらにちょっと修正してみた結果。
剣の姫巫女≪メイデン≫と大命者≪ヘスター≫(仮)
あいざわゆう
第一章:
「あたしピカティ、今この街におりますの。助けて、ください」
「はい?」
僕は思わず声を上げた。
その「啓示」は、突然ネットを渡ってきた。
今日は、週の真ん中の水曜日。
僕が、一面茜色に染まる空の下、学校の帰り、秋津洲市と呼ばれるこの街の、ターミナル駅の前にスクールバスから降りた。
その時、メガネ型透過ディスプレイの片隅に、ツイッターのダイレクトメッセージを示すアイコンが点滅した。
ん、なんだろう。こんな時にダイレクトメッセージなんて。
そのメッセージアイコンを、脳波で押した。
DMの名前と彼女を示すアイコンと共に表示された、先程のメッセージに、一気に目が覚めた。
彼女の名前は、ピカトリクス(ピカティ)・フィメル・アミール・イスマイル・フィルーン。
彼女は、向こうの世界<ザウエニア>のイズマイル王国という国のお姫様で、絶賛お姫様ライフ中だ。
ザウエニアとは、異世界との接触の時に最初に地球に接触した、魔法がある世界でありながら、地球をはるかに超えた科学技術なども持ち合わせた異世界だ。
僕の父親、ルシャーム・メル・アミール・ハティム・マルカーンの故郷≪ふるさと≫でもある。
正確に言うと、世界名は<アークシャード≪天空のかけら≫>と言う。
ザウエニアとは、アークシャードにある、北アメリカ大陸に似た大陸のことを指したり、そこにある神々と皇王、その下にいる国王などが治める、幾つもの国が集まって構成されている皇国を指すこともある。
そんな異世界アークシャードに住んでいるはずのピカティが、どうしてこの地球に、この秋津洲に、いるんだ?
それに……。『助けて、ください』って……。
僕は急いで電話機能を開き、ピカティの個人電話番号にかける。
素早くリストを選択。名前を押す。国際電話番号を使わずにだ。
電話は、すぐに繋がった。世界間通信でよくある長めのタイムラグはない。
ということは、この地球にいるのか?
携帯の念話スイッチを入れる。
今の時代のスマホは、精神波を読み取り、言葉を念じるだけでそれを音声に変換し、相手に送ることができるのだ。
これで他の誰にも内容を聞かれることなく、話ができる。
「もしもし、ピカトリクス王女様?」
「はいー」
聞き慣れた、優しく甘くて気品ある声が日本語で返ってきた。たしかに姫様だ。
術法やボイスチェンジャーで声を変えているのでなければ、だが。
それはともかく、聞きたいことを聞いてみる。
「なあ、今本当に秋津洲におられるのですか?」
「はい。いますの」
「おられますか」
「いますの」
それはそれとして、王女様、転送門≪ポータル≫でこっちにやってきたのか……。
久しぶりだなあ。
それはともかく、聞きたいことはまだある。
むしろそっちがメインだ。
「……どうしてこっちに来られたのですか?」
僕がそう言った瞬間、電話はぷつっと、切れた。
「もしもし? もーしもーし?」
だが、耳元から聞こえるのは、プーップーッという電子音のみ。
ふぅっ。……しょうがない。こっちから出向くか。
僕は神殿街へと足を向けた。
幾つものJR線や私鉄、それに新交通システムなどが乗り入れる秋津洲駅は、いつも人でごった返している。
いつもの光景。いつもの場所。
それがなんだか、くっきりと輪郭を持って見える。
神殿街は、駅からやや離れたところに入り口がある。
新交通の駅が神殿街の近くにあるけど、そう大した距離ではないし、歩いていこう。
今僕がいるのは、秋津洲駅前だ。
今は古い、建設当時は未来的なデザインの駅ビルやデパート、都市ビルが並び立つこの街は、異世界人たちが数多く居住する国際都市になっている。
地球人から見れば見慣れない建物や、見たことのない文字のアドホログラム≪看板≫などがここからでも見える。
バスターミナルに面した通りでは、ここかしこで異界の鮮やかな民族衣装の人間や、見た目が人間とはまるっきり違う二足歩行型生物や、意識を持って歩く人間型ロボットなどの異世界人、そして日本人や外国人といった地球人たちが行き交っている。
一般の日本人からしてみれば、そこは日本ではない、いや、地球ですらないどこかにいるようにも錯覚する、エキゾチックで魅惑的な場所だ。
そんな人々の間をすり抜けながら、僕はザウエニア人街に向かう。
早くピカティの待つ、ザウエニア人神殿街のファスラム教神殿≪モスク≫へと行こうか。
と、その時、突然、ディスプレイに着信のアイコンが忙しく光った。
相手は……、もちろんわかってる。王女様だ。
僕は脳波コントロールで電話機能を立ち上げる。
「もしもし?」
すると、先ほどと同じ、抑揚のないきれいな声が聞こえてきた。
「今パブコにおりますの。……ちょっと、急ぎます」
パブコというのは、ザウエニア人街の近くにある大型デパートのことだ。
ちょっとずつは近づいてきているらしい。
「ちょっと待っててください。すぐ参りますので」
僕がそう言うと、電話はすぐに切れた。
……姫様、お聞きになられてるのかなー?
僕はパブコへと足どりも軽く向けようとした。
と、そう言えば。
王女様、向こうで神殿で姫巫女≪メイデン≫の修行をしてて、この間、全修行を終えたとおっしゃっていたっけ。
彼女からはこの間、そちらのご修行はいかがですか? なんて尋ねられたけど。
そんなことを考えながら、僕はピカトリクスがいるというバブコへと向かっていた。
大型家電量販店が入居している、商業ビルディングなどの間を通る通りを通りぬけ、大通りの横断歩道で青信号を渡る。
細めの通りを入ったところにあるアミューズメントセンター「ラッシー」の前に来た時だった。
その時、メガネ型ディスプレイにまた着信のアイコンが輝いた。着信アイコンにスイッチ。
「もしもし?」
その問いに帰ってきた返事が聞こえたその瞬間、気分も、世界も、一八〇度変わった。
「今ラッシーの中におりますの。はやく、きて」
「ラッシー!?」
俺は思わず、ホログラムの飛行機が屋上に乗っかって輝いている、赤い建物を横目で見ながらすっとんきょうな「声」を上げる。
「い、今参ります」
そう言うとまた不意に電話は切れた。
なんてこった……。姫様がこんなに早くこっちに近づいてきているなんて……。
何故か、背筋に冷たいものが走る。
ともかく、行かなきゃ。
僕はラッシーのガラス張りの自動ドアの前へと進む。
入るとすぐそこにはゲーセンらしく、薄暗い空間の中に、いくつものゲーム機があった。
入った瞬間に、電子音と人工音声が両耳を覆い尽くす。
目の前には、白いドームがいくつも並んでいる。
少し遠くには、そのドームに大きさなどは似ているが、形やデザインの違う筐体がそれぞれまとまって置かれている。
それらはすべて「マジカルリアリティゲーム」の筐体だ。
マジカルリアリティゲームは異世界からもたらされた技術によって、実現したゲームだ。
<アークシャード>などからもたらされた、世界を創造する「魔法」によって作られた人工空間に、プレイヤーが入り、様々なルールのもとでプレイする、バーチャルリアリティゲームがさらに進化したゲームの事だ。
でも、どちらかというとマジカルリアリティゲームよりも、昔のゲームのほうが好きかなあ、僕は。そっちのほうが面白いし。
シバレスだからという理由で、絡まれるということもないし。
様々な形や色のドーム群の間をすり抜け、ピカティの姿を探す。
しかし、それらしい姿は視えない。
どうしたんだろう……、姫様。また移動しちゃったのかな……。
そう訝しんだ時、ディスプレイの隅に、着信アイコンが光った。急いで電話に出る。
「もしもし?」
しばらくの無言。
……ま、間違い電話かな?
と思った時。
彼女が、今までとは違ったおどろおどろしい声で、続けた。
「……今、アナタの後ろにおりますの!」
「え……?」
え……!? ま、まさか……!?
僕が恐る恐る振り向くと。
そこには真っ白な一枚布に包まれたような人影が、佇んでいた。
まるで都市伝説の少女、メリーさんのように!
「いたあああああああ!!」
次の瞬間、僕は思わず絶叫してしまった。
怖えええ!? 怖えええよなにこれ!?
目の前の白い布に覆われていた幽霊のような人影はしばらく佇んでいたが、腕らしき場所を動かすと、頭の部分に手をかける。
……一体何が出てくるんだ!?
ゴーストか!? ファントムか!? それともヴァンパイアだったりする!? ねえ!?
人影は頭のフードを取る。その間の黒い影から現れたのは……。
「もう、何を驚かれているんですか、カツヤさまっ?」
長い黒髪を後頭部でまとめた、可愛らしい美少女の顔だった。
彼女のその目はくりっとしていて、紫がかった黒。
目のバランスは全体からしてみると大きいが、とても可愛げがあって美しい。
肌の色は雪色で、頬の雪原に赤い花畑が咲いていた。
一対の目の間にそびえる鼻は、低くもなければ高くもなく、綺麗に尖っている。
そして小さく可愛げの有る口。
それらのパーツが、両耳にたれた黒髪の間の小さな顔の中に、最も調和している位置に置かれていた。
彼女はどことなく、庭に咲いた一つの小さな桜の木のようにも思えた。
ほっ……。間違いない。
「あ、ああ……。おひさしぶりです。ピカトリクス王女様……」
目の前にたたずむ幽霊の正体は、見間違わなかった。
ザウエニアにあるイスマイル王国の美姫。ピカトリクス・フィメル・アミール・イスマイル・フィルーン王女だった。
彼女が脱いだフードの間から、体に焚き染めた香の芳しい香りが届いてくる。
ああ……。この気持ちいい匂い。間違いない。ピカティの体の香りだ。
僕は胸に手を当てて一礼した。
秋津洲学園では様々な世界の王族・貴族などの、上流階級の子息などが留学していることも多いので、こうした礼儀作法は小等部の頃から習わされている。
王女は、あ、うん。この場ではね……。というような表情をしてから、深々とおじぎを返す。
「お久しぶりでございます、カツヤ・ズルカルナイン・メル・アミール・ハティム・石塚・マルカーン様。あら、なんでそんなにびっくりなされているのですか……?」
硬直している僕を、ちょっと理解できない、という目で見る。
「そりゃそうだっ!! 突然後ろに幽霊みたいのがいたらだれでも驚くわっ!?」
そんな僕に王女はすました顔で、
「あら、幽霊≪アンデッド≫なんて、ザウエニアにはいくらでもいますし、そんなに驚かなくても……」
「……これだからザウエニア人は……」
「あら、カツヤ様だってザウエニア人でございましょう……?」
「くっ……」
僕は、喧嘩をしている犬のように睨む。
しかし、敵意を露わにしているのは僕の方で、ピカティはどこ吹く風、余裕の表情だ。
ピカティめ……。
……ん? 僕ら、いや、ピカティに注がれている熱い視線がある……?
素早く周りを見回す。
すると、周りのゲームの順番待ちやプレイを見学していた男達の目が、ピカティの美貌に注がれていた。
彼らの顔は、一様に下衆だ。
……お前ら、姫様をジロジロと見るなよ! こんなところから、すぐに出なきゃ!
次の瞬間、僕はピカティの白くて細い手を取り、引っ張る。
「ピカティ王女様。ここじゃ人の目もありますし、別の場所へ参りましょう」
「え……!? は、はい……!」
2月 5, 2014 水曜日 at 2:22 pm