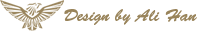スマッシュ(完成)
鳥のように大空を飛び回ることも、手のひらから虹色のビームを出すこともできないのだと、この世に生まれてから、一体何時頃に人は気づくのだろう。身体が大きくなるにつれて、眼の前に広がる世界からそういった魅力的な色彩が色褪せていくことを、いつのまにか当然のように受け止め、そうすることでなんとか生きのびていっている。
そんな状態を、誰に不満を言うわけにもいかず、というより、不満というほどの明確な形になってないこのぼんやりとした感情が、自分の生活の大部分を占めてるのかもしれない、最近そんなことを考えてばかりいる。
靄がかかった赤色のゴム皮に、まるで食欲をそそられない人工的なクリームを塗りつけている今だって、そうだ。珍しく部活の練習場に一番乗りしたからといって、台の準備をして今更下級生にいい人アピールしたくも無ければ、一人壁打ちやシャドーをするほど酔狂でもなかった。
遠くのほうでバレー部の女子が飽きもしないで騒ぎたてながらネットを設置している。知られるはずもないのに、生ぬるく毛恥ずかしい感情を背負って座り込んでいる姿を誤魔化そうと、両足をハの字に開いて上体を倒していくことにした。正直ストレッチなんて、意味がよくわからないけど、こんな風に時間をつぶしながら「活動しているアピール」するにはちょうどいい。まるで学校行事みたいだ。腹這いから上体を反らしてみると、斜め前に置かれたカラーボックスに、部費で買った卓球雑誌が乱雑に置かれているのが目に入った。自分よりも年下のくせに、卓球をかじったことのある人なら知っているくらいの有名選手が、こっちを見すえてラケットを振りかぶっている。
例えば、彼らなら。いやもっと、プロとかなら。中国や欧州の世界トップ選手達なら。プレイしているその世界は、どんな風にみえているのだろう?ひょっとしたら、スマッシュを打つ瞬間には、ビームとまではいかなくても空気を切り裂く音くらいは聞こえているのかもしれないな。
16年も人間をやってきたというのに、それでもまだ、時折こんなことに思いを巡らせてしまうのは、結局のところ、自分はまだどこかで、そんな夢物語に対する憧れを捨てきれない「子ども」なわけで。例えば10年後、多分どっかの大学を出て、なんかわからないけどどっかの会社で働いて、社会に出て数年もしたら、こんな感情も消えてしまうんだろうか。そうなればそれは随分楽なことのようでもあり、どことなく空恐ろしい感じがするようでもある。
バカバカしくてうっとおしいこの想念を冷まそうと、エビ反りの体勢からうつ伏せになって全身で床の冷たさに触れていると、さっき磨き終わったラケットがすぐ傍で所在なげにしていた。相変わらず黒くよごれて、全体的になんとなくむくんでいる。このあいだ、カッターナイフとサンドペーパーでいい加減に削った持ち手だけが不自然に白い。けど、どうせそれも、いつのまにか周りと同じように同化し、目立たなくなってしまうんだろう。
女子じゃあるまいし、今時日ペンで、それもスレイバーなんて使い続けているのだって、意地になってるわけじゃない、と思う。周りには金欠だなんて平凡な言い訳をしていたが、別に本音にしたって、卓球をはじめた時から使い続けていて替えるのはなんとなく気がひけるという程度の、たいしたものじゃない。ただ、これ見よがしにラバーを変えては感想を言い合い、研究熱心を装うメンバーとは、ほどほどの距離以上には入りたくなかったし、入らせてもらえなかった。技術も熱意も才能も、俺にはそんなグループに入るレベルですら備わっていなかった。
結果、同じような立場の友人と、1台を占拠して、ただただオール練習を続け、飽きたら休憩。その繰り返しでいつの間にか終わるのが、部活というものになっていた。
そんな人間が公式戦にすら出させてもらえなかったのは、ある意味当然なわけで。メンバー発表を聞く前からもう試合とかは諦めていたから、補欠登録とかいう心遣いはかえってうっとおしかった。
いつの間にかそんな連中がいつも通りやってきて、下級生が台を慎重に押していく傍で雑談しながら入念にラケットの手入れを始めている。次の試合に選ばれた方たちは本当に熱心で頭がさがる。どうせ、名門でも強豪でもない普通高校の運動部の部活にそこまで熱意を持てるのは、一体なんなんだろう。何も考えてない純粋さなのか、内申点のためのアピールなのか?それにしたって、どうせ大した推薦なんてあるわけじゃないだろうに。かすかに嫉妬の匂いがする疑問の視線を、そんな連中に向けながら、今日もまた、それなりに楽しく虚しい時間つぶしを始めるために、立ち上がっていた。
「お前さぁ」
「何」
「まじで、ツッツキばっかなのな、ずっと」
「何をいまさら」
卓球なんてそんなもんでしょ、とまで言い続けようとするのが、なんとなく途中で口ごもってしまった。もちろん、「そんなもん」じゃない卓球があることは知ってる。でもそれは、確実性のあるミート打ちやカット、強力なドライブ、いわば自分には到底届かないようなそれら輝かしい様々な技術があって初めて到達可能なんであって、そこに至るまでには、平凡な一高校生が、多分一生かけても届かないの凄まじい努力とか才能とかが要求される、だから。だから、自分にはないものねだりをしたってしょうがないじゃないか。
「バックに下回転ふっとけば絶対速く来ないから、結局その後のラリーにポジションしんどくなって負けちゃうじゃん、いつも」
そんなの、本人が一番わかってる。そして、それが自分の持つ力では、どうしょうもないことも、痛いくらい。
だって、しょうがない。輝かしい世界を見れるのは、そういう選ばれた一握りの人達で。自分はその中に入ってない。そんなことは、今までにいやになるほど感じさせられてきた。結果、いつの間にか自分に染み付いたのは、ひたすらツッツキで試合を進め、我慢比べの結果、ボールをコントロールできずにミスをするのを待つだけの卓球だった。自分にとても良く似合っていて笑えてしまう。そう、わかってる。数えきれないほど練習して、それなりに色々なことができるようになって、結局わかったことは、あくまで「それなり」にしか俺にはできないってこと。よほど読みきれるか、チャンスボールか、運がいいか、そんな限定条件でないと、絶対安全確実じゃないとこの右腕は振りきれない。こわばってしまって、動かない。危険を犯して攻めにいくなんて、言葉はカッコいいけど実際は無残に散るし勝率も下がるだけだ。こんな不安定な時代にリスクをとれとか夢を叶えろとか無責任な期待も指導もしないでほしい。
友人の言葉から始まった自己弁護の想念が、やや前よりバックにスライスされてきたボールに対する一歩目を鈍らせた。なるべく慌てない素振りで伸ばしきった腕からのバックドライブの先から、ボールが白い風船みたいに台の上を景気良く飛び越えていく。
「珍しく振ったと思ったらホームランかい」
考えてみれば、これからのことだってそうなのかもしれない。我慢の続く日々で、ときどき気休めみたいなイベントがあって。その喜びとか痛みを反芻しながら生きながらえていく。多分あと、今までの何倍かくらいの時間。
「ごめん」
上の空で小さくつぶやいて、友達の横を通り過ぎ、ボールを迎えに行くことにした。多分なんか、色々諦めながら。
薄汚れた白色のピン球が茶色の床をのんきに転がっていく。手を伸ばすと、埃のうっすら積もったカラーボックスに並んだ卓球雑誌が、ふと目に入った。さきほどの年下有名選手が、変わらないまま必死の表情でこっちを見つめている。ご苦労さんなことだ。すごいよな、ほんと。多分、この子もすごい小さな頃からすごい練習させられてすごい倍率で勝ち抜いてきて今ここに載るくらいになって。これからもまだまだ、そんな無間地獄のような日々を続けていくんだろうか。
そういえば、自分は、このくらいの頃何してたんだっけ。あ、そうだ。このスポーツをはじめたのは丁度このくらいだったか。初めてラケットを自分で買ったのは、小学校だったか。店頭に飾られたラケットを目にした時、初めてボールにあたった時、初めてスマッシュが相手を突き抜けていった時。その瞬間。自分の手の中にあるのは、最強の武器で最高の相棒みたいで。自分はそのとき、間違いなく神に選ばれしヒーローだった。世界の主人公は疑うことなく自分で、顔一面が熱くなって、その火照りが苦しくって、それでも必死になって飛び跳ねている。自分の全能感を信じて、酔いしれて。
笑っちゃうくらいちっぽけなそんな思い出に、でも今になるまですがりついている。まだこんなに鮮明に、覚えているくらいには。きっとその時はその時なりに、色々なうっとおしさを感じていきてたんだろう。あるいは、そんなことすら感じなかったか?でも、今それから10年がたって、ここにこうしてあるときには。それだけのことが、こんなに輝いて思えるものなんだな。それはひょっとしたら、まだこれから今までの何倍も続く人生の中で、すがりつかざるをえないような、意味を持つことなのかもしれない。
「さんきゅー」
いつのまにか、秋季大会メンバーで次期部長候補さんからの流れ弾が、足元にじゃれついてきていた。首にかけたタオルで汗を拭い、ラケットを上げてこちらに声をかけてくるのは、日々勉学に励み、周囲と良好な関係を保ちながら、部活に打ち込んでいる、何処からも文句の出ないような模範的な卓球部所属の高校生の姿だ。
そんな姿を見ていると、つい今湧いて出たこの思いつきが、急速に現実味を帯びてきたように思えた。足元のピン球を拾い上げながら、少しずつ胸の底が粟立ってくるのを感じる。
じゃあ、10年後。今日今からすることは、やっぱりそんな風に。意味を持つのかな?
そんなことを考えながら、努めて落ち着いたような声で話しかけた。
「なあ、ちょっといい?」
「え?」
「今から、少しやらない?ゲーム。3セット先取で」
何時以来だろう。点を取るたびに声が出るなんて。
タオリングが習慣じゃなく必要なほど額に汗を掻く感触が、懐かしい。わざとじゃなくて、はぁはぁ言ってないと、マジで呼吸がしんどいくらい、肺を動かして。
そして、3グラムもないような軽いピンポン玉に、ここまで集中する時間は、ひょっとしたらはじめてかもしれない。
周りはきっと、わけがわからないんだろう。別に大会前の選抜選考でもない、こんな時期のただのゲームに、ここまで入れ込む奴なんて、馬鹿としか思えない。
いいじゃないか、構わない。むしろそのほうが、自分らしい。
こいつがそういう場になって、本気で準備して本気で勝負にきたら、きっと俺は、あっけなく終わる。だから。だから、今日一度だけ、10年後に俺が生きていくためのチャンスをくれ。
いい加減、横目で見ていてお前のやり方だってわかってる。
左右のカバーはほとんどシェイクの両面ドライブで、ショートに対してはストップ気味にカット。そのコースをバックに流せないのは、あれだけ練習してもこんなに切羽詰まってくるとどうしょうもなくなるんだな。
だったら、いくら俺でも準備しておいてフリック強打気味にするくらいはできる。抜けるか、たとえリターンできてもその崩した体勢で逆サイドにとびつくのは、無理だろう?
「あぁぁあああああっ!!!」
相手のいないバックにまっすぐボールの軌跡が突き抜けていくのを確認するかしないかくらいのタイミングで、また、自然に口が開く。喉の奥から叫びが飛び出す。
相手を威圧するんじゃなくて、自分自身に聞かせるために。自分は今、あと2点取れば、初めてこの、優秀な次期キャプテンに勝てて、未来のための価値を作ってて、そんなことどうでもよくなるくらい、必死なんだって。あとで見たら恥ずかしくなるくらい真剣になって、狂え狂えって自分に言い聞かせてる。
目先を変えるために狙ってきた下回転サーブが、右ネット際のサイドラインを2センチくらい飛び越えて落ちていく。伸ばした右手のその先の、ラケット先端を必死に押しとどめる。頼む。止まれ。
「ナイセン」
久々に声を掛けてくれたな、お前。ありがとう。余裕を見せたい振りしてくれて。人の悪いにやけ顔を、床を見つめることで何とかごまかそうとする。
デュースが8回目。そろそろいい加減、限界だろ?この馬鹿馬鹿しいゲームを、終わりにしたいだろう?だったら、一番よく使ってるサーブに、無意識にでも頼るしかなくなるよな。
ほら、気持ちバック側に寄ってやるから。もっかい、打ってこい。今のサーブ。さっきよりも慎重に、アウトしない程度に加減した威力で。
・・・ほんとはフォアに飛び込むつもりしかないから、バックなんて来たらお手上げだったんだけどな。
勝利した賭けの余韻を片隅で味わいながら、左足で床を蹴る。着地した右足が、全身の体重を支えて、もう一度左足に。おもいっきり床を踏み鳴らして、最後の気持ちを奮い立たせる。
ゲームの途中から、気づいていたことがある。いいや、本当はずっと、毎日いろんなとこで感じていて、確信を持ったんだ。
本当のスマッシュは、憧れているあの世界の光景っていうのは、きっと。小手先の我慢比べの先とか、相手の不注意につけこむとか、そんなところにあるんじゃなくて。
今、自分からいく。決意した、その瞬間に。相手もまるで考えてないような、後からみたら馬鹿にされるような、でも自分にとって譲れない、気持ちが振っ切れた時に叩き込むんだって。
丁度、今みたいな時に。
思い切り、腕のどっかの関節がぱきっていうくらい、大きく右腕を開く。
多分、鳥が大空を飛ぶときみたいに。ひょっとしたら知らないうちに、体育館一杯に響き渡るくらい声も出てるかもしれない。知ったこっちゃない。違う。遅い、もっとだ。もっと。早く速く、ためらわずに振る。もう、失敗も相手も将来とかもうかがうな。
ピン球めがけて、呪いのようにまとわりつき続けるよく分からないものをおもいっきり殴りつけた右腕が、目の前の世界を駆け抜けていった時。
いつの間にか、端のほうからゆがみはじめていた世界が、辺り一面、白くなったように感じた。
2月 19, 2015 木曜日 at 11:12 pm